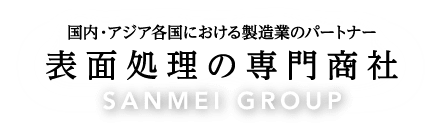商品のご案内
Products
≪ 表面処理 ≫
亜鉛メッキ及び亜鉛合金メッキ
|
酸性浴 |
亜鉛(酸性浴) |
特徴
(1)本来、鉄は単体でなく鉄鉱石として埋蔵されています。鉄は人為的に精錬されて作られるものですから、時間が経つにつれて元の姿に戻ろうとします。これが腐食の現象です。鉄が元の姿に戻らないよう、しっかりした腐食対策を講じることが大変重要になります。
(2)鉄の防食として、もっとも有効な技術のひとつとして亜鉛めっきです。鉄素材に亜鉛めっきを行う事により鉄を外気から遮断し陽極的な挙動で鉄(貴)より電位の低い亜鉛(卑)の腐食が優先されピンホールを生じても犠牲陽極作用により亜鉛が溶解し鉄を保護します。
亜鉛めっき自身は大気中で酸化されやすいので防錆と外観向上のため後処理としてクロメート処理、化成処理を施します。
(2)鉄の防食として、もっとも有効な技術のひとつとして亜鉛めっきです。鉄素材に亜鉛めっきを行う事により鉄を外気から遮断し陽極的な挙動で鉄(貴)より電位の低い亜鉛(卑)の腐食が優先されピンホールを生じても犠牲陽極作用により亜鉛が溶解し鉄を保護します。
亜鉛めっき自身は大気中で酸化されやすいので防錆と外観向上のため後処理としてクロメート処理、化成処理を施します。
用途
亜鉛めっきは自動車部品、電気機器部品、建築、事務機などの多くの分野で使用されている。冷蔵庫、洗濯機などの電気機器や事務機はほとんど亜鉛めっき鋼板が使用されている。
浴種
従来はシアン浴の市場占有率が高かったが、公害問題以降、ジンケート浴や塩化浴が増加した。特に東南アジアや中国、欧米に日系企業が進出する際には、ほとんどジンケート浴か塩化浴が使用される。
【1.アルカリ浴】
・シアン浴(高濃度浴、中濃度浴、低濃度浴)
・ジンケート浴
【2.酸性浴】
・塩化亜鉛浴(カリ浴、アンモン浴、ナトリウム浴)
【1.アルカリ浴】
・シアン浴(高濃度浴、中濃度浴、低濃度浴)
・ジンケート浴
【2.酸性浴】
・塩化亜鉛浴(カリ浴、アンモン浴、ナトリウム浴)
【塩化浴】
塩化浴は古くから鉄板、電線の高速連続めっきなどに使用されていた。均一電着性が悪く、粗雑なめっきになるなどの欠点があったが光沢剤の改良により欠点が補われた。めっき速度が速い浴として特にバレルめっきで使用されるようになった。
塩化浴の主成分となるアンモニウムが作業範囲の広さから多く使用されていたが窒素の排水規制が厳しくなってきたため、アンモニウムの一部をカリに代替したアンモニウム・カリ折衷浴やカリ浴が多く使用されるようになった。カリ浴の緩衝剤として使用されているホウ酸についても、ホウ素の排水規制が厳しくなり早急に対策をする必要がある。ナトリウム浴は作業範囲が3浴の中で最も狭いためほとんど使用されていない。
【物性比較】
評価:良 A > B > C 悪
塩化浴は古くから鉄板、電線の高速連続めっきなどに使用されていた。均一電着性が悪く、粗雑なめっきになるなどの欠点があったが光沢剤の改良により欠点が補われた。めっき速度が速い浴として特にバレルめっきで使用されるようになった。
塩化浴の主成分となるアンモニウムが作業範囲の広さから多く使用されていたが窒素の排水規制が厳しくなってきたため、アンモニウムの一部をカリに代替したアンモニウム・カリ折衷浴やカリ浴が多く使用されるようになった。カリ浴の緩衝剤として使用されているホウ酸についても、ホウ素の排水規制が厳しくなり早急に対策をする必要がある。ナトリウム浴は作業範囲が3浴の中で最も狭いためほとんど使用されていない。
【物性比較】
評価:良 A > B > C 悪
| 物性 | シアン浴 | ジンケート浴 | 塩化浴 |
| 光沢 | B | B | A |
| 2次加工性 | A | B | C |
| 硬度(HV) | 80〜120 | 100〜140 | 50〜80 |
| 水素脆性 | C | B | A |
| ウイスカー | A | C | C |
浴成分の働き
【塩化浴】
亜鉛濃度が低いと高電流部分にコゲ易くなり高くなるとつきまわり性や低電流部分の光沢が悪くなる。
塩化アンモンが低下すると導電性が低下し、つきまわり性、低電流部分の光沢が悪くなる。多くなると光沢剤の溶解性が下がり液が濁ることがある。
光沢剤にはベース成分と呼ばれる一次光沢剤と光沢・レベリング成分と呼ばれる二次光沢剤がある。一次光沢剤が少ないとコゲ易くなり、二次光沢剤成分が少ないと光沢が低下する。両方とも多いと物性が悪くなりめっきが欠け易くなる。
pHが低すぎると光沢範囲は狭くなり、高すぎると液が濁り易くなる。
【性能比較】
評価:良 A > B > C 悪
【評価の捕捉】
鋳物めっき:鋳物にめっきした場合の難易度の評価。
耐食性:後処理(クロメート、3価クロム化成処理)後の耐食性の評価。
耐前処理:前処理の影響の度合い。
亜鉛濃度が低いと高電流部分にコゲ易くなり高くなるとつきまわり性や低電流部分の光沢が悪くなる。
塩化アンモンが低下すると導電性が低下し、つきまわり性、低電流部分の光沢が悪くなる。多くなると光沢剤の溶解性が下がり液が濁ることがある。
光沢剤にはベース成分と呼ばれる一次光沢剤と光沢・レベリング成分と呼ばれる二次光沢剤がある。一次光沢剤が少ないとコゲ易くなり、二次光沢剤成分が少ないと光沢が低下する。両方とも多いと物性が悪くなりめっきが欠け易くなる。
pHが低すぎると光沢範囲は狭くなり、高すぎると液が濁り易くなる。
【性能比較】
評価:良 A > B > C 悪
| 性能 | シアン浴 | ジンケート浴 | 塩化浴 |
| 電着速度 | B | A | A |
| 均一電着性 | B | A | C |
| 被覆力 | C | B | A |
| 鋳物めっき | C | C | A |
| 耐食性 | C | A | B |
| 浴管理 | A | B | B |
| 耐前処理製 | A | B | B |
| 排水処理 | C | A | C |
| 設備腐食性 | A | A | C |
【評価の捕捉】
鋳物めっき:鋳物にめっきした場合の難易度の評価。
耐食性:後処理(クロメート、3価クロム化成処理)後の耐食性の評価。
耐前処理:前処理の影響の度合い。
メッキ法
ラックめっき、バレルめっ