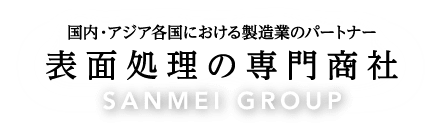商品のご案内
Products
≪ 表面処理 ≫
工程
|
銀メッキ |
銀メッキ |
特徴
銀は金と共にもっともよく知られた貴金属である。銀は他の金属では真似られない明るい白色を持つ。金と同様に数千年前から宝飾品や通貨として用いられてきた。
用途
銀はスプーンやフォークなど高級銀製食器にめっきされるが、銀は抗菌性に優れている。もう一つ、光反射性に富んでおりこれも特徴である。銀めっきの用途は下記のように装飾用途と工業用途に分類される。
【表1 銀めっきの用途】
【表1 銀めっきの用途】
| 応用範囲 | 応用分野 | 応用例 |
| 工業用途 | 電気機器 | 開閉器、遮断器 |
| 電子機器 | コネクター、リードフレーム、導波管、銀めっき綿状 すべり接点、無線電話、自動車電装部品、PC、衛生テレビ |
|
| 反射特性 | 照明機器、鏡 | |
| 殺菌特性 | 外科設備、衛生器具 | |
| 装飾用途 | 一般商品 | 宝飾品、時計、眼鏡、筆記具、ライター |
| 食堂用途 | 食器類、テーブル備品 | |
| 工業意匠 | 容器、金具 |
性質
銀は金属の中でももっとも電導性が良く。最小の電気抵抗率を示す。
一般の人の予想に反して、電気抵抗率の順位は銀<銅<金の順になる。銀は酸化性の酸には侵されないが、硝酸または熱濃硫酸には容易に溶解する。銀は硫黄または硫黄化合物に対して弱く、硫黄化合物の存在する雰囲気で容易に黒褐色の硫化銀皮膜を生成する。したがって銀めっきにとって変色防止は重要課題である。
一般の人の予想に反して、電気抵抗率の順位は銀<銅<金の順になる。銀は酸化性の酸には侵されないが、硝酸または熱濃硫酸には容易に溶解する。銀は硫黄または硫黄化合物に対して弱く、硫黄化合物の存在する雰囲気で容易に黒褐色の硫化銀皮膜を生成する。したがって銀めっきにとって変色防止は重要課題である。
浴種
銀めっきの大部分はアルカリ性シアン化銀めっき浴で、むしろ非シアン浴h例外である。
シアン化銀カリウムKAg(CN)2を主原料とする。これは銀イオンの錯塩である。無色透明の
結晶で水に良く溶ける。シアン化銀めっき浴はこの他に次の成分を含む。
・遊離シアン化カリウムKCN又はシアン化ナトリウムNaCN
・炭酸カリウムK2CO3
・水酸化カリウムKOH
・光沢剤
・硬化剤
シアン化銀めっき浴では可溶性の純銀アノード(>99.9%)を使用する。遊離シアンは銀アノードの溶解に必要な成分である。遊離シアン濃度が低いと銀アノード溶解が不調になり、めっきも白っぽくなる。逆に遊離シアン濃度が高いとアノード溶解が促進されて、銀の結晶がキラキラ光って結晶模様になる。同時に均一電着性が改善されるが、電流効率は低下する。遊離シアン濃度と錯塩濃度の比率は2:1〜1.5:1であるが、光沢めっき浴ではもっと高くなる。炭酸カリウムは、空気中の炭酸ガスの吸収によって濃度が増加する。低濃度の時には浴の電導性と均一電着性に寄与するが、炭酸カリウムの濃度が100g/Lに達すると、低電流部分の光沢が悪くなるので、凍結法などで濃度を下げる必要がある。苛性カリKOHは高速度めっき浴に電導塩として加える。
光沢剤又は硬化剤には、次のような物質が使用される。
・硫化炭素化合物(二硫化炭素)
・無機硫黄化合物(チオ硫酸ナトリウム)
・有機化合物(スルフォン酸塩)
・セレン又はテルル化合物
・周期律表4B又は5B族金属(アンチモン、スズ、亜鉛、ビスマス、砒素)
【<銀ストライクめっき浴について>】
金と同様に銀は電気化学的に貴な為に銀めっき浴中に卑金属を浸漬すると、銀が置換析出して密着不良を起こす為に、銀ストライクめっきが必要になる。銀ストライクめっき浴は他のストライクめっき浴と同様に、低金属濃度、高遊離シアン濃度の浴を使用し、室温でやや高めの電流密度を使用する。厳密には素材の種類によって浴や条件を変える必要がある。銀ストライクの前にNiストライク浴(ウッド浴)でストライクめっきすると、密着性は確実に良くなる。
素材別(鉄及び銅素地)のストライクめっき浴は下記のようになる。
【<装飾用光沢銀めっきについて>】
装飾用途の銀めっきには完全鏡面光沢が要求される。その為に、素材は完全に研磨され、下地めっきされた状態で銀めっき工程に入る。光沢剤の種類によって色調が違うので、導入の際には予備実験が必要である。光沢剤の中には長時間使用すると、光沢剤の分解生成物の蓄積による老化が起こり、めっき膜の応力が高くなり、密着不良を生じたり、光沢不良になる場合があります。定期的にめっき液の更新が必要。
代表的なシアン化銀めっき浴は下記のようになります。
シアン化銀カリウムKAg(CN)2を主原料とする。これは銀イオンの錯塩である。無色透明の
結晶で水に良く溶ける。シアン化銀めっき浴はこの他に次の成分を含む。
・遊離シアン化カリウムKCN又はシアン化ナトリウムNaCN
・炭酸カリウムK2CO3
・水酸化カリウムKOH
・光沢剤
・硬化剤
シアン化銀めっき浴では可溶性の純銀アノード(>99.9%)を使用する。遊離シアンは銀アノードの溶解に必要な成分である。遊離シアン濃度が低いと銀アノード溶解が不調になり、めっきも白っぽくなる。逆に遊離シアン濃度が高いとアノード溶解が促進されて、銀の結晶がキラキラ光って結晶模様になる。同時に均一電着性が改善されるが、電流効率は低下する。遊離シアン濃度と錯塩濃度の比率は2:1〜1.5:1であるが、光沢めっき浴ではもっと高くなる。炭酸カリウムは、空気中の炭酸ガスの吸収によって濃度が増加する。低濃度の時には浴の電導性と均一電着性に寄与するが、炭酸カリウムの濃度が100g/Lに達すると、低電流部分の光沢が悪くなるので、凍結法などで濃度を下げる必要がある。苛性カリKOHは高速度めっき浴に電導塩として加える。
光沢剤又は硬化剤には、次のような物質が使用される。
・硫化炭素化合物(二硫化炭素)
・無機硫黄化合物(チオ硫酸ナトリウム)
・有機化合物(スルフォン酸塩)
・セレン又はテルル化合物
・周期律表4B又は5B族金属(アンチモン、スズ、亜鉛、ビスマス、砒素)
【<銀ストライクめっき浴について>】
金と同様に銀は電気化学的に貴な為に銀めっき浴中に卑金属を浸漬すると、銀が置換析出して密着不良を起こす為に、銀ストライクめっきが必要になる。銀ストライクめっき浴は他のストライクめっき浴と同様に、低金属濃度、高遊離シアン濃度の浴を使用し、室温でやや高めの電流密度を使用する。厳密には素材の種類によって浴や条件を変える必要がある。銀ストライクの前にNiストライク浴(ウッド浴)でストライクめっきすると、密着性は確実に良くなる。
素材別(鉄及び銅素地)のストライクめっき浴は下記のようになる。
| 鉄素地用 | 銅素地用 | ||
| シアン化銀カリ | 1.4〜2.8g/L | シアン化銀カリ | 5.6〜8.3g/L |
| シアン化ソーダ | 60〜150g/L | シアン化ソーダ | 60〜90g/L |
| 温度 | 20〜25℃ | 温度 | 20〜35℃ |
| 電流密度 | 1.5〜2.5A/dm2 | 電流密度 | 1.5〜2.5A/dm2 |
| 時間 | 1〜2分 | 時間 | 30〜60秒 |
| 陽極 | ステンレス板 | 陽極 | ステンレス板 |
【<装飾用光沢銀めっきについて>】
装飾用途の銀めっきには完全鏡面光沢が要求される。その為に、素材は完全に研磨され、下地めっきされた状態で銀めっき工程に入る。光沢剤の種類によって色調が違うので、導入の際には予備実験が必要である。光沢剤の中には長時間使用すると、光沢剤の分解生成物の蓄積による老化が起こり、めっき膜の応力が高くなり、密着不良を生じたり、光沢不良になる場合があります。定期的にめっき液の更新が必要。
代表的なシアン化銀めっき浴は下記のようになります。
| 組成と条件 | 濃度(g/L) | ||
| I | II | III | |
| シアン化銀塩(金属として) | 25〜33 | 25〜33 | 36〜114 |
| 遊離KCN | 30〜45 | - | 45〜160 |
| 遊離NaCN | - | 30〜38 | - |
| K2CO3 | 30〜90 | - | 15〜75 |
| Na2CO3 | - | 38〜45 | - |
| KOH | - | - | 4〜30 |
| 電流密度(A/dm2) | 0.5〜1.5 | 0.5〜1.5 | 0.5〜1.0 |
| 温度(℃) | 20〜25 | 20〜25 | 38〜50 |
メッキ法
浸漬
技術解説
銀メッキ工程について
【1.電気関係の物(銅・黄銅素材)】
アルカリ脱脂→水洗→化学研磨→水洗→酸洗→水洗→中和→水洗→銅ストライク→水洗→銀ストライク→(水洗)→銀めっき→水洗→(変色防止)→熱風乾燥
【2.食器、トロフィーなど素材研磨を必要とする物】
黄銅・洋銀素材→研磨(グロース・傷はペーパーで取る)→仕上研磨→引掛け→アルカリ脱脂→電解脱脂→水洗→中和→水洗→酸浸漬→水洗→光沢ニッケルめっき→水洗→中和→水洗→銀ストライク→(水洗)→銀めっき→水洗→湯洗→乾燥→バフ仕上げ(赤棒)
【3.鉄系素材の物】
アルカリ脱脂→水洗→電解脱脂→水洗→20%塩酸→水洗→5%シアン化ナトリウム溶液で陰極処理→水洗→20%塩酸→水洗→中和→水洗→銅ストライク(orニッケルストライク)→水洗→銀ストライク→銀めっき→回収→水洗→変色防止→乾燥
アルカリ脱脂→水洗→化学研磨→水洗→酸洗→水洗→中和→水洗→銅ストライク→水洗→銀ストライク→(水洗)→銀めっき→水洗→(変色防止)→熱風乾燥
【2.食器、トロフィーなど素材研磨を必要とする物】
黄銅・洋銀素材→研磨(グロース・傷はペーパーで取る)→仕上研磨→引掛け→アルカリ脱脂→電解脱脂→水洗→中和→水洗→酸浸漬→水洗→光沢ニッケルめっき→水洗→中和→水洗→銀ストライク→(水洗)→銀めっき→水洗→湯洗→乾燥→バフ仕上げ(赤棒)
【3.鉄系素材の物】
アルカリ脱脂→水洗→電解脱脂→水洗→20%塩酸→水洗→5%シアン化ナトリウム溶液で陰極処理→水洗→20%塩酸→水洗→中和→水洗→銅ストライク(orニッケルストライク)→水洗→銀ストライク→銀めっき→回収→水洗→変色防止→乾燥
硬質銀メッキについて
コネクタ、スイッチ、摺動部分などに使用する銀めっきは、一般に硬質銀めっきと言われている。銀めっきは、光沢剤に微量の金属(亜セレン酸、アンチモン、ビスマス等)を添加する事により、硬さを増す。しかし、電子部品の場合に光沢剤として銀以外の金属を含む事は電気特性上好ましくない。そこで、無添加の銀めっきをめっき後にバレル研磨して表面硬化させている場合もある。
高速度部分銀メッキについて
高速度部分めっきは、従来のラック又はバレルめっきで行ってきた全面めっきと異なり必要な部分だけマスキングして高電流密度でめっきを行う事である。この方法により、1μ/秒くらいの高速度でめっきが出来る。高速度銀めっきには、遊離シアンのない中性浴が用いられる。
高速度銀めっき浴の例は下記のようになります
高速度銀めっき浴の例は下記のようになります
| 無光沢浴 | 半光沢浴 | |
| 銀濃度(g/L) | 65 | 65 |
| 添加塩 | PO42-,NO3 | PO42- |
| 温度(℃) | 60 | 60 |
| pH | 8.0〜8.5 | 8.0〜8.5 |
| 電流密度(A/dm2) | 10〜100 | 30〜150 |
| ヌープ硬さ | 50〜80 | 120〜180 |
| 光沢剤 | - | As,Se,Te,メルカプタン類 |
銀メッキの変色防止法について
銀めっきの最大の欠点は、硫黄又は硫黄化合物の存在する環境で変色する事である。銀めっきの変色防止には色々な方法が提案されてきた。しかし、どの方法も長期間の変色防止は不可能である。
変色防止方法には次の4種類に分類出来る。
1.有機皮膜及びラッカー
2.異種金属めっき膜
3.クロメート膜
4.スズ膜
上記の中で主として?と?のグループが使用されている。銀の変色は不動態膜とは異なる難溶性の皮膜に起因する。銀は純粋の空気中で極めて薄い酸化膜を生じる。銅と違って高温度で変色しない。銅の場合には酸素と結合して酸化銅になるが、銀上の酸素は銀表面から発散していく。大気中に硫化水素が存在すると、酸化銀膜を作る事無く、極めて難溶性で黒褐色の硫化銀の皮膜で覆われる。
変色防止方法には次の4種類に分類出来る。
1.有機皮膜及びラッカー
2.異種金属めっき膜
3.クロメート膜
4.スズ膜
上記の中で主として?と?のグループが使用されている。銀の変色は不動態膜とは異なる難溶性の皮膜に起因する。銀は純粋の空気中で極めて薄い酸化膜を生じる。銅と違って高温度で変色しない。銅の場合には酸素と結合して酸化銅になるが、銀上の酸素は銀表面から発散していく。大気中に硫化水素が存在すると、酸化銀膜を作る事無く、極めて難溶性で黒褐色の硫化銀の皮膜で覆われる。
有機皮膜
油やワックス溶液に浸漬するだけの簡単な方法である。電子部品には、溶剤に溶かしたワックスが古くから使用されている。品物をワセリン容積に浸漬後、溶剤が蒸発すると保護膜が残る。しかし、この種の皮膜は薄いので、処理後の取扱に耐えない。装飾分野では、焼付けラッカーや樹脂膜が採用される。これらは比較的硬いので、摩耗や洗浄に対して非常に強い。ラッカー面はゆっくりと劣化する。工業分野では、最近チオール膜が利用され、好結果を得ている。この方法では、銀がチオールと結合すると硫化銀を作らないという性質を利用する。この皮膜によって、高濃度の硫黄を含む環境での銀表面の変色を防止する事が出来る。同時にこの皮膜は接触抵抗を高める事無く、接点のすべり特性を改善する。この皮膜は外的な傷を受けても自己治癒性があり、硬化しない。半田付けにも影響を与えない。成膜には気相法も可能であるが、主として浸漬法で行われる。
異種金属メッキ膜
ロジウム、金又はパラジウムを銀表面に薄くめっきする事によって、かなりの長期間銀の変色を防止する事が出来る。中でもロジウムは色調が銀と似ているので、もっとも多く使用される。使用例は工業用途に多く、めっき厚さは0.1〜3μmの範囲である。
クロメート膜
クロメート膜により、短期間の変色防止が出来る。浸漬法又は陰極電解法が適用出来るが、後者の方が有効である。銀表面に透明ないし淡黄色のクロメート膜が出来る。皮膜は機械的外傷に弱い。また、複雑部品の隅の部分までは防食されない。使用例は、電気製品の意一時防食である。この方法は、6価クロムを含むので、環境問題から用途は限定される。
スズ膜
銀の変色防止にスズ膜が使用される事がある。スズの色調は銀と似ているからである。60%以上のSnを含むSn-Cu合金はスペキュラムと呼ばれ銀白色なので、銀の上に薄くめっきして変色防止膜とする事も出来る。実用性は色調に依存する。この他、Sn単体の電気めっきや各種Sn水溶液からのSn膜を置換析出させる方法もある。